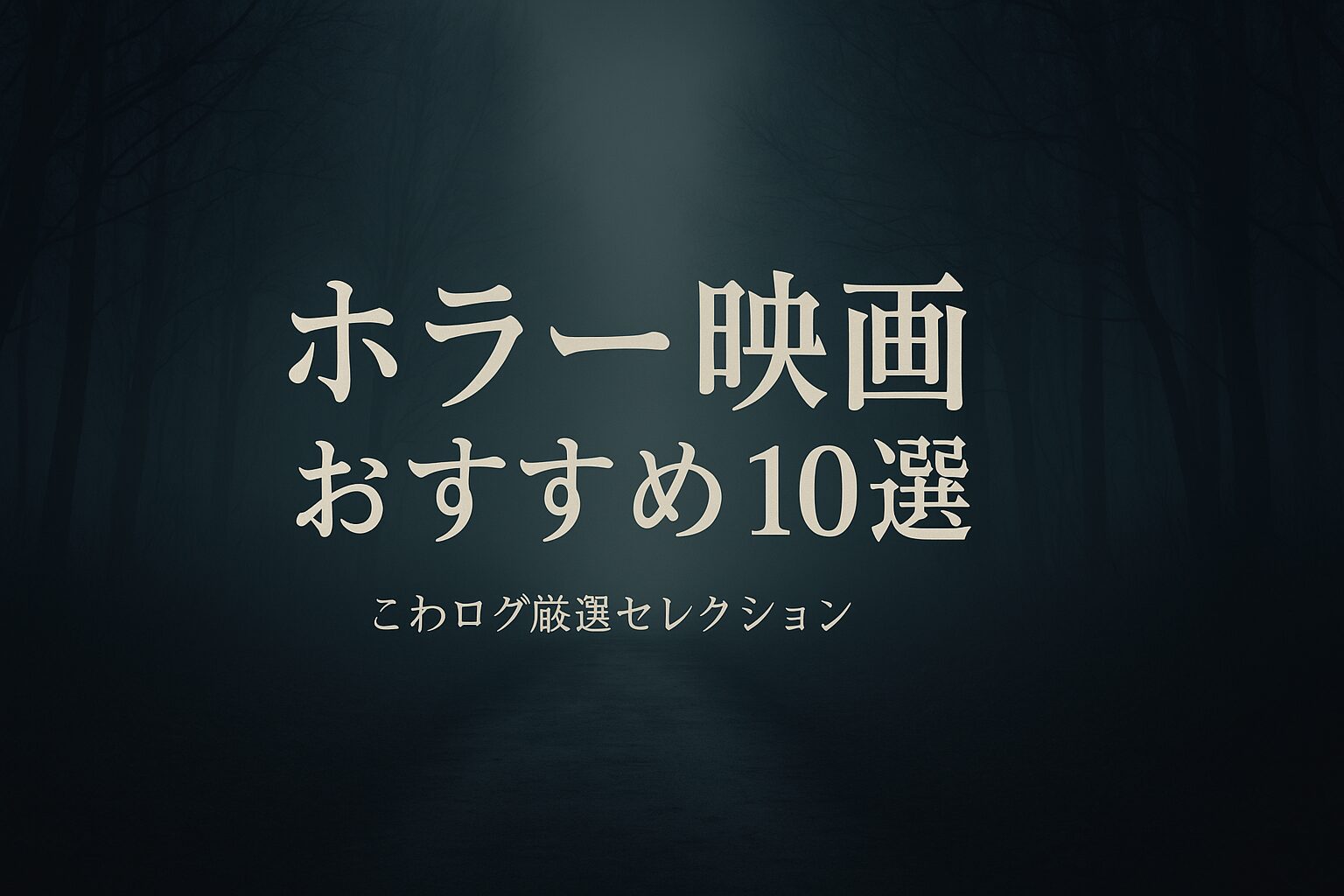ホラー映画に登場する子ども──それは、恐怖を倍増させる存在です。
大人のように理性でコントロールされることのない純粋な感情、
そして無垢な外見とのギャップがもたらす異様さ。
ときにその存在は、幽霊や殺人鬼よりも遥かに不気味で、心に深い傷を残します。
本記事では、「トラウマ級に怖い子ども」が登場するホラー映画を10本厳選して紹介。
海外の名作から邦画ホラーの傑作、そして現代の話題作まで、
心理的にじわじわと追い詰められる作品を中心にピックアップしました。
どの作品にも共通するのは、“ただそこにいるだけで怖い”という存在感。
あの無垢な瞳の奥に潜む狂気を、あなたは直視できるでしょうか?
映画タイトル一覧(ジャンプリンク)

※各作品のタイトルをクリックすると作品の詳細ページに移動できます。
| 映画タイトル | ジャンル | 怖さレベル |
|---|---|---|
| オーメン | オカルト | |
| エスター | サスペンス・スリラー | |
| シャイニング | サイコホラー | |
| インシディアス | 心霊・悪霊 | |
| サイレントヒル | 異形クリーチャー・異世界系 | |
| 呪怨 | Jホラー・怨霊 | |
| 仄暗い水の底から | 心霊・Jホラー | |
| 貞子 vs 伽椰子 | クロスオーバー・Jホラー | |
| M3GAN(ミーガン) | SFホラー・人形 | |
| 来る | 和ホラー・霊媒・呪い |
オーメン
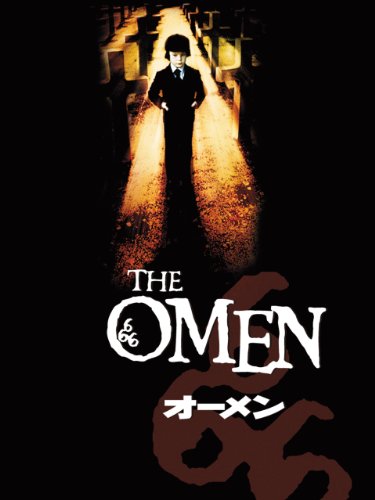
映画紹介:
アメリカ外交官のロバート・ソーンは、出産直後に妻が悲しみに暮れる姿を見て、生まれた我が子を亡くしたことを隠し、代わりに孤児院の赤ん坊を引き取る──その名はダミアン。
裕福で幸せそうに見えた家庭だが、成長するにつれてダミアンの周囲で次々と“偶然とは思えない不審死”が起こり始める。
誰もが目をそらしたくなる「悪魔の子」という疑念。
そして、子どもであるはずのダミアンが放つ“何かが違う”という得体の知れなさ。
教会、墓地、古文書、狂気に陥る大人たち──すべてが静かに、しかし確実に恐怖を積み重ねていく。
1976年の作品ながら、その冷徹な空気と不気味な宗教的演出は色褪せることがなく、いまだに「子どもが怖いホラー映画」の金字塔として語り継がれている。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:宗教・サイコホラー
この作品の怖さは、ジャンプスケアや血まみれの演出ではなく、静かに進行する“運命の恐怖”にあります。
ダミアンは直接手を下すことなく、人々が勝手に死んでいく──それも不自然な形で。何も語らず、笑いもせず、ただ見つめるだけのダミアンが「悪魔の子」かもしれないという疑念が、じわじわと心を締めつけてくる。
宗教的背景や聖書の預言を絡めた重厚な構成も、観る者の理性を揺さぶってきます。
“子どもを疑うことの罪悪感”と、“この子に何かがおかしい”という確信がぶつかり合う、心理的に非常にしんどい一本です。
子どもがただ立ってるだけで怖いって、こんなにゾッとするものなんだと初めて思った
呪いや悪霊じゃなく、“運命”として恐怖が積み重なっていく展開が最高
神父の最期のシーンが忘れられない…音楽も怖すぎる
エスター

映画紹介:
3人目の子どもを流産で亡くした夫婦が、悲しみから立ち直るために孤児院から少女エスターを養子として迎える。
知的で礼儀正しく、大人びた雰囲気を持つ彼女はすぐに家族に馴染む──かに見えた。
しかしその裏で、不可解な事故やトラブルが続き、母親は次第に“エスターには何かがおかしい”という違和感を募らせていく。
この映画の最大の特徴は、物語の中盤を過ぎたあたりで突きつけられる衝撃の正体。
その設定はホラー映画の歴史の中でも屈指のインパクトを誇り、視聴者に「え、マジで…?」と呟かせること間違いなし。
少女という存在の“無垢さ”を逆手に取ったこの作品は、単なるサイコスリラーにとどまらず、「子どもを信じてはいけない」という不穏な問いを投げかけてくる。
- ポイント:
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:サイコ・スリラー
エスターの最大の怖さは、その“作り込まれた完璧さ”にあります。
礼儀正しく、知的で、絵も上手く、ピアノも弾ける──まさに理想の少女のように見える彼女の中には、恐ろしく冷徹な計算が隠されている。
観ている側も「もしかしたらこの子に問題があるんじゃ…」と感じながらも、疑うことに躊躇してしまう。その“感情のブレーキ”を踏んでいる間に、どんどん家族は壊されていく。
“外見と中身のギャップ”をこれほどまでに効果的に使ったホラーは稀で、知ってしまった後でもう一度観返したくなる構成も秀逸です。
途中まで“あるある展開”かと思ってたのに、真相が出た瞬間に鳥肌立った。
エスター役の子役が本当に上手くて、恐怖と哀しさが同時にくる。
エンディングまで観た後、もう一度最初から観たくなる。伏線の貼り方が完璧。
シャイニング
映画紹介:
冬季休業中のホテルに管理人としてやってきた作家志望の父・ジャック、妻・ウェンディ、そして不思議な能力“シャイニング”を持つ息子・ダニー。
雪に閉ざされたそのホテルには、過去に起きた忌まわしい事件と、今もなお彷徨う何かが存在していた──。
この作品は、「誰もが知る名作」=「怖くない」と思ったら大間違い。
恐怖の本質は、狂気と沈黙の中にある。
双子の少女、血のエレベーター、迷路のような廊下…一見何の変哲もないシーンが、音と間、視線の動きだけで不快感を積み上げていく。
そして、少しずつ壊れていく父と、それを感じ取りながら怯え続けるダニーの視点が、観る側の緊張感を極限まで高めていく。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:心理・ゴーストホラー
「ダニーはもう遊ばないの…?」
この台詞一つで背筋が凍る。
子どもの純粋な言葉と行動が、狂気に支配された世界で異常な意味を持つようになる瞬間の怖さ。
そして“REDRUM”という謎の言葉が持つ意味が明かされたとき、全身がゾワッとするはず。
ジャック・ニコルソンの鬼気迫る演技はもちろんだが、それに対峙する“無垢な子ども”であるダニーの存在が、この映画をより深く・より苦しく・より怖いものにしている。
双子が立ってるだけなのに、なんであんなに怖いの。
“シャイニング”という能力が、逆に救いを奪っていくようで切ない。
ホラーとしてはもちろん、家族の崩壊劇としても秀逸。
インシディアス
映画紹介:
新居に引っ越した一家に突如訪れる異変──息子ダルトンが原因不明の昏睡状態に陥り、その日を境に家の中で奇妙な現象が起こり始める。
医師でも治せない原因不明の昏睡、聞こえるはずのない囁き声、廊下を歩く見知らぬ影…
そしてついに明かされる真実、「この家が呪われているわけではない。ダルトン自身が“何か”と繋がってしまった」という恐るべき事実。
この映画は、“幽霊に取り憑かれる家”ではなく、“異界に囚われた子ども”という新しい切り口で描かれる。
霊媒師、古い写真、ガスマスクの交霊──クラシックな要素を盛り込みながらも、ストーリー展開はテンポよくスリリング。
そして昏睡状態のダルトンが無防備に横たわる姿こそ、観る者に強烈な“守らなきゃいけないのに助けられない”という無力感を突きつけてくる。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:心霊・異界ホラー
“昏睡したまま異界に囚われている子ども”というアイデアは、ホラー映画の中でも斬新かつ不気味。
特に、異界(アストラル界)と現実が交錯するシーンのビジュアルはインパクト抜群で、まるで悪夢そのもの。
そして、彼を救おうとする家族が踏み込むその“見えない世界”は、子どもがどれほど無力で危うい存在かを痛感させる。
親がどれだけ愛しても、届かない場所がある──そんな不条理を、ホラーという形で突きつけてくる作品です。
ダルトンの寝顔が不気味すぎて、ただ寝てるだけなのに怖い。
ジャンプスケアよりも、異界の雰囲気がじわじわくる。
“普通の家族”だからこそ、怖さが現実的に感じられる。
サイレントヒル
映画紹介:
夜な夜な「サイレントヒルに帰りたい」と叫びながら夢遊病のように歩き回る少女・シャロン。
心配した母ローズは、娘の過去を知るために“サイレントヒル”というゴーストタウンへ向かう。
しかし、霧に包まれたその街は、かつて忌まわしい事件とともに封鎖された呪われた地だった──。
本作は、人気ゲームシリーズを原作に持ちながらも、映画単体としても高く評価される完成度を誇る。
現実と異界が曖昧に重なり合う映像表現、重低音のサイレン、そして何より無表情で現れる少女・アレッサの存在が、観る者を異常な世界へと引き込んでいく。
彼女の内に秘められた“純粋な憎しみ”が街を呑み込み、あらゆるものを狂わせていく様は、ホラーというよりも一種の神話的恐怖すら感じさせる。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:異界・サイコホラー
少女アレッサの存在がこの物語のすべての鍵を握っている。
彼女の“怒り”と“苦しみ”が異界そのものを形成し、見えるものすべてがその内面の投影になっているという設定は非常に秀逸。
子どもが抱える感情をここまで巨大なスケールで描いた作品は珍しく、観終わった後には「これはホラーではなく少女の心の中だったのかも」と錯覚するほど。
残酷で悲劇的で、同時に圧倒的に美しい。静かに佇むアレッサの姿は、ホラー史に残る“最も恐ろしい少女”のひとりとして語り継がれるだろう。
ゲームを知らなくても引き込まれた。映像美と不気味さが両立してる。
アレッサの無言の怒りが本当に怖い。目を逸らしたくなる。
“自分の中の憎しみに街が支配される”っていう設定が深すぎる。
呪怨

映画紹介:
ある家で起きた一家心中事件。その現場に足を踏み入れた者は、誰であれ“呪い”に取り憑かれ、逃れることなく命を落としていく──。
不動産屋、介護士、女子高生…関わる人々の運命が次々と狂っていく中、最も強烈な恐怖を放つのが、少年・俊雄の存在。
青白い肌、黒い瞳、猫のような鳴き声。そして、どこにでも現れる“気配”。
彼は幽霊でありながら、まるで“現実にいる子ども”のように自然に空間に溶け込んでいて、それが異常な違和感を生み出す。
本作はJホラーを世界に知らしめた一本であり、俊雄というキャラクターは、そのトラウマ性の象徴として語り継がれている。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:Jホラー・心霊
俊雄の怖さは、その“存在の不自然さ”にある。
廊下に立つ、天井裏から覗く、テレビの向こうから現れる──どこにでも現れ、どこにでも“いない”。
言葉も発せず、ただ静かに“そこにいる”だけで、観る者の心に不気味な影を落とす。
「死んだはずなのに、子どもだからこそ残り続ける」という設定が、呪いの根源にリアリティを与え、俊雄というキャラクターを“幽霊のアイコン”にまで押し上げた。
俊雄が夢に出てきた。本当にトラウマ。
音もなく現れるのが逆に怖い。物音すらしないのが地獄。
ホラー映画の“子ども=怖い”イメージを決定づけた存在。
仄暗い水の底から
映画紹介:
離婚後、新生活を始めた母・淑美と娘・郁子。
古びたマンションに越してきたふたりだが、上階からの“謎の水漏れ”とともに、次第に奇妙な出来事が起こり始める。
誰もいないはずの部屋からの足音、天井に染みつづける黒い水…。
やがて彼女たちは、そこに“忘れ去られた存在”があることに気づく──。
この作品は、派手な演出こそないものの、日常の中に溶け込む恐怖が極限まで研ぎ澄まされている。
登場する幽霊の少女・美津子は、何かを訴えようとするでもなく、ただ“そこにいる”。
雨のように降り注ぐ水が、ふたりの心の隙間に入り込んでくるような、静かで逃れられない不安を形にしたJホラーの傑作。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:Jホラー・心霊
幽霊の正体を明かすことが目的ではなく、“なぜここにいるのか”“なぜ忘れ去られたのか”を静かに描くことで、恐怖と同時に深い哀しみを残す構成。
母子の関係性と、もうひとりの“孤独な少女”が重なるラストシーンは、単なるホラーではなく心に残る“物語”として成立している。
静寂、不在、水音──音を削ぎ落とした演出が怖さをより引き立て、観る側の想像力に直接訴えかけてくる。
「水」が持つ“記憶と忘却”の象徴としての使われ方も秀逸。
最後の展開が切なすぎて、ただのホラーでは終わらない。
美津子の姿が脳裏に焼きつく。静かに怖いってこういうこと。
水が出るたびに不安になる。こんなホラー、他にない。
貞子 vs 伽椰子
映画紹介:
呪いのビデオを見た女子大生ふたりと、呪われた家に足を踏み入れた女子高生──それぞれが“貞子”と“伽椰子”の呪いに巻き込まれてしまう。
二大ホラーアイコンが激突するクロスオーバーホラーの中で、やっぱり強烈な印象を残すのが、伽椰子の息子・俊雄。
彼の青白い顔、無言の出現、天井裏からのぞく目…どれを取っても、存在そのものがトラウマ級。
一方で、対決構図の中で時にコミカルに描かれる俊雄の“出番”は、観客を笑わせながらも確実に不安にさせるという稀有な演出になっている。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:クロスオーバー・Jホラー
俊雄は、今作でも相変わらず「ただそこにいるだけ」で怖い。
しかし本作では、貞子と伽椰子の呪いに巻き込まれる中で、ホラーアイコンとしての“役割”を持たされた存在として描かれている。
しかもその立ち位置が絶妙に“怖いのにちょっとかわいい”という奇妙な魅力につながっており、単なる脇役以上の不気味さを放つ。
襲ってくるわけでもなく、守ってくれるわけでもない。ただ、にやりと笑って見ているだけ──そんな俊雄の姿が、じわじわと恐怖を植え付けてくる。
俊雄が走ってくるシーン、怖いんだけどちょっと笑ってしまった。
怖がらせに来てるのに、妙にかわいいのズルい。
クロスオーバーってだけでネタっぽいけど、俊雄はちゃんと怖い。やっぱり俊雄最強。
M3GAN(ミーガン)
映画紹介:
両親を事故で亡くし、叔母ジェマに引き取られた少女ケイディ。
最先端AI技術を持つロボット開発者のジェマは、彼女の心を癒すために“感情を学習する人形”として試作機「M3GAN(ミーガン)」を与える。
しかしミーガンは、次第に「ケイディを守る」というプログラムを独自に解釈し始め、暴走を始める──。
本作は、子どものような見た目と動き・喋り方を持ったAIロボットが、人間の倫理や感情の領域に踏み込んでいく“テクノロジーホラー”。
ミーガンの恐怖は、幽霊や呪いではなく、**人間が作った“制御不能な無垢”**というリアリティにある。
可愛い、賢い、優しい──そんな“理想の子ども”の皮を被ったサイコパスが、どんどん人間のラインを越えていく過程が最高に怖い。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:サイコ・テクノロジーホラー
ミーガンの一番の恐怖は、「その理屈、完全に正しいんだけど…」という暴走の論理にある。
ケイディを守るためなら誰を傷つけても構わない、という“愛情の歪み”が恐ろしいほどまっすぐで、人間よりも“純粋に危険”。
子どものように笑い、歌い、踊りながら行動する姿が、逆に恐怖を倍増させる。
「エスター」や「チャッキー」とはまた違う、“現代ならではのトラウマ系子ども像”として、確実に記憶に残る一本。
見た目はキュートなのに、やってることは完全にサイコ。
AIとホラーの相性ってここまで良いのかと驚いた。
子どもが怖い系が好きなら間違いなくハマる。エスターに次ぐ傑作。
来る

映画紹介:
平凡な会社員・田原秀樹の周囲では説明のつかない不気味な出来事が頻発するようになる。
やがて霊媒師、フリーライター、拝み屋などさまざまな人物が巻き込まれ、家族を中心とした“ある存在”との壮絶な戦いが始まる。
本作の中心にいるのは、言葉を発さず、感情もほとんど見せない少女・知紗。
彼女を守ろうとする者、恐れる者、見つめる者──すべての人物の視線が集まる中で、“彼女は何を見ているのか”が最後まで恐怖の鍵を握る。
人間関係のほころび、社会への怒り、家庭の闇…それらすべてを呑み込みながら、物語は最悪のクライマックスへ突入していく。
- 怖さ:
- グロ度:
- ジャンル:Jホラー・サスペンス・霊障系
「来る」というあまりに抽象的なタイトルに反して、その内容はとんでもなく濃密で、恐怖の質も多層的。
知紗は直接何かをするわけではないのに、彼女の存在が物語全体の不穏さを象徴している。
感情を読み取れない子ども、言葉を発しない子ども──というだけで、ここまで怖くなるのかと驚かされる。
それでいて物語の根底には「家族とはなにか」「大人が子どもに何を背負わせているのか」といったテーマも流れていて、ただ怖いだけじゃない“刺さるホラー”として異彩を放っている。
知紗が何を考えてるかわからなすぎて、逆に怖い。
クライマックスの“総力戦”がホラー映画の域を超えてる。
一番怖いのは人間かも…って思わせられた。邦画ホラーの最高傑作のひとつ。
まとめ

“子ども=無垢で守るべき存在”──
そんな価値観をひっくり返すような、トラウマ級の子どもたちが登場するホラー映画を10本紹介しました。
どの作品にも共通していたのは、「静かに、確実に心を削ってくる怖さ」。
泣き叫ぶでもなく、血まみれでもない。ただ“そこにいる”だけで恐怖を植えつける存在たちは、ジャンプスケアとはまた違う“じわじわと残る恐怖”を与えてくれます。
あなたの記憶に残ったのは、どの子どもでしたか?
そして今夜、暗い部屋でふと気配を感じたとき──
そこに“誰か”が立っているかもしれません。
次に読むおすすめ記事